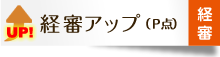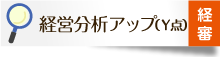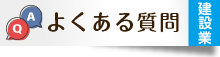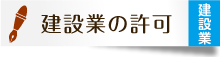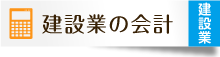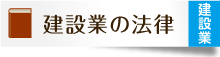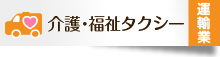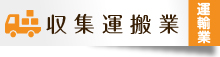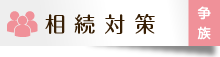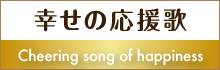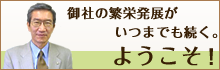「収益性・効率性」の一つである「総資本売上総利益率」について、説明いたします。
この「総資本売上総利益率」の寄与度は21.4%もあります。この寄与度21.4%は、「負債抵抗力指標」の一つである「純支払利息比率」の寄与度29.9%に次ぐ、2番目に寄与度が大きい指標です。「純支払利息比率」の寄与度29.9%+「総資本売上総利益率」の寄与度21.4%=51.3%になり、経営分析の寄与度の半分以上を占めます。したがって「総資本売上総利益率」も重要な経営指標の一つになります。
|
(算式は) 総資本売上総利益率=売上総利益/総資本(2期平均)×100で計算します。 |
売上総利益とは、簡単に売上高から売上原価を差し引いた金額です。通常、粗(あら)利益という言葉で表現されます。売上高は完成工事高+兼業事業売上高であり、売上原価は完成工事原価+兼業事業売上原価です。経営状況分析では兼業事業も含めた金額で、粗利益を計算します。
総資本とは、総資産と同じ金額で、いわゆる貸借対照表の総資産金額です。負債と純資産の合計額でもあります。全投下資本ともいえます。総資本の2期平均ですから、直前決算期と前期決算期の平均です。
つまり、粗利益を総資本で割ったものに100を掛けて、%(百分率)で表した指標が、総資本売上総利益率です。当然にこの指標が高いほど収益性が良いことになります。経営状況分析では、総資本売上総利益率の上限値は63.6%で、下限値が6.5%です。
この指標の見方ですが、例えば、総資本1億円の会社が粗利益500万円を稼ぎますと、総資本売上総利益率は500万円÷10,000万円×100=5%になります。また、総資本5千万円の会社が粗利益500万円を稼ぎますと、総資本売上総利益率は500万円÷5,000万円×100=10%になります。下記のとおりです。
|
総資本(総資産) |
1億円 |
5千万円 |
|
売上総利益(粗利益) |
500万円 |
500万円 |
|
総資本売上総利益率 |
5% |
10% |
|
(高い方が良い) |
低い |
高い |
同じ500万円の粗利益でも、総資本5,000万円の会社の方が、経営状況分析では優秀な会社になります。小さな総資本で粗利益を大きく稼ぐことが、この指標のポイントになります。
この指標をアップするには、総資本を減らすか、粗利益を増やすかの2つです。