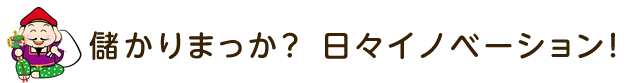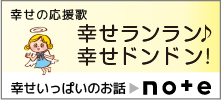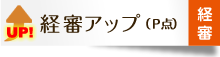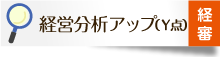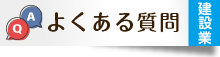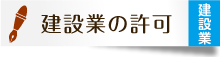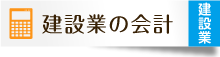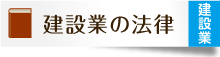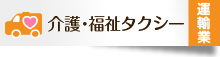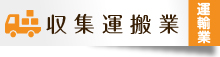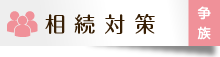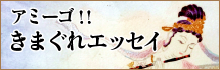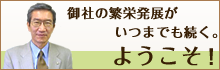令和7年4月1日から施行される改正トラック法を簡単に説明いたします。
「改正貨物自動車運送事業法 Q&A」から紹介させていただきます。
Q&Aの総論の問1-1に「改正トラック法の概要を教えてください」とあり、答えは次のように書かれています。
従前より貨物自動車運送事業において、多重下請構造や口頭による運送契約の締結等が、適正な運賃・料金の収受に当たっての大きな課題となっていました。
そうした課題に対応するため、今般、トラック法を改正し、
1.運送契約締結時等の書面交付義務
2.下請事業者の健全な事業運営の確保に資する取組(健全化措置)を行う努力義務、当該取組に関する運送利用管理規程の作成、運送利用管理者の選任義務
3.実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成・保存義務
などの規制的措置を導入することとしております。
ただし、今回の改正トラック法が適用される事業者は、すべての貨物運送事業者に義務付けされるわけではありません。
Q&Aの問3-7には「具体的にどのような事業者が義務付けの対象になりますか」の答えは、次のとおりです。
前年度に行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量(以下「利用運送量」という)が100万トン以上である一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者が、「運送利用管理規程の作成」「運送利用管理者の選任義務」の対象となります。貨物利用運送事業者は義務付けの対象にはなりません。いわゆる「水屋業」と呼ばれる貨物利用運送業者は対象になりません。
要するに、一般貨物運送事業者が対象になりますが、実車運送(自社便)ではなく、利用運送の年間取扱量が100万トン以上の事業者が対象になりますので、100万トン未満の運送事業者は対象になりません。
Q&Aの問3-7-2には「過去に一度でも100万トン以上となったことがあれば、義務付けの対象となるのでしょうか」の答えは、次のとおりです。
令和6年度以降に利用運送量が100万トン以上となった場合に義務付けの対象となります。令和5年度以前の利用運送量は問いません。
以上のとおり、一般貨物運送事業者で、令和6年度の利用運送量が100万トン以上の場合に適用されます。その場合には、運送利用管理規程を作成して届出なければなりません。また、運送利用管理者の選任届出書も必要になります。
それぞれの様式は、国土交通省のHPに掲載されています。