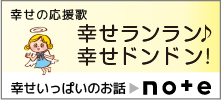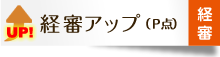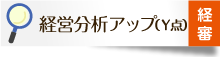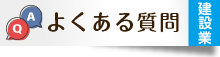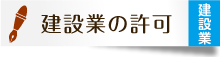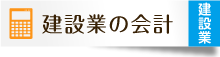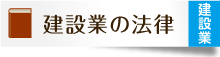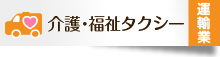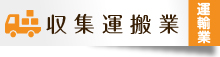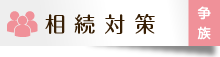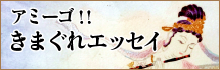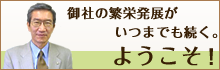取引相場のない株式(自社株)の評価方法の流れで説明しましたように、自社株の評価方法には、「類似業種比準価額方式」「純資産価額方式」「併用方式」「配当還元方式」があります。
大会社は、「類似業種比準価額方式」または「純資産価額方式」で評価します。
中会社は、「併用方式」または「純資産価額方式」で評価します。
小会社は、「純資産価額方式」または「併用方式」で評価します。
特定会社等に該当する場合は、「純資産価額方式」で評価します。
同族株主等以外に該当する場合は、「配当還元方式」で評価します。
それでは、純資産額方式の説明に入ります。
1.純資産額方式で評価する場合、いつの時点の数値で評価しますか
原則として、課税時期(相続や贈与のあったとき)において仮決算を行い、その数字により評価することになっています。
ただし、期の途中において仮決算を行うことは困難なことも多いため、直前期末の決算数値を基に評価することも認められています。この場合は、直前期末からの資産および負債に著しい増減がなく、評価額の計算に影響が少ないと認められる状況である必要があります。実務的には、直前期末の数字を使うことがほとんどです。
なお、課税時期が直後期末に非常に近く、課税時期から直後期末までの間に、資産および負債に著しい増減がないと認められる場合は、直後期末の金額で評価することもできます。
ただし、資産および負債について、課税時期から直後期末の間に、経理操作を行っているなどの課税上の弊害がある場合は、直後期末の数字で評価することはできません。
2.純資産額方式の概要
純資産価額方式は、現段階で会社が解散したと仮定して、株主に返ってくる1株あたりの純資産価額で評価する方式です。
本来、会社の資産は全て株主のものですから、「仮に会社を解散させたら、株主にどれぐらいの財産が返ってくるか」という考え方に基づいています。主に規模の小さな会社の評価に用いられます。
課税時期現在の相続税評価による資産及び負債の金額で判断します。帳簿価額で判断しません。もっとも帳簿価額で判断するものもありますが、あくまで相続税評価額による総資産の価額、相続税評価額による負債の価額で評価します。
1株当たりの純資産価額は、次の式に当てはめて計算します。
|
①総資産の価額-②負債の価額-③評価差額の法人税等相当額(注)=④純資産の価額 ④純資産価額/発行済株式数=1株当たりの評価額 |
①総資産の価額も、②負債の価額も、④純資産の価額も、当然に相続税評価額によって計算金額です。帳簿価額ではありません。
ここで注意すべきは、③評価差額の法人税等相当額をマイナスしていますが、単純に法人税相当額をマイナス出来るわけではありません。あくまで評価差額の法人税等相当額ですので、含み益に対する法人税等です。
評価差額に対する法人税等相当額の計算式は、次のようになります。
|
〔(①総資産の価額-②負債の価額)-(帳簿価額による総資産の価額-帳簿価額による負債の価額)〕×37%=評価差額に対する法人税等相当額(含み益に対する法人税等) |
もっと簡単な式にすれば、次のようになります。
|
評価差額に対する法人税等相当額=〔純資産(時価) - 純資産(帳簿価額)〕× 37% |
ここでいう時価は、相続税評価額です。
おそらく、土地の評価などで含み益がなければ、評価差額に対する法人税等相当額(含み益に対する法人税等)は、ゼロに近い数字になり控除できません。
もう一つ注意すべき事は、純資産価額方式で計算した結果、議決権割合が50%以下の同族株主グループに属する株主が取得した株式の価額は、通常の規定により計算した純資産価額(相続税評価)の80%相当額となります(評価通達185のただし書き)ので、間違わないようにしましょう。
あとは、課税時期の決算書(通常、直前期末)に基づき、現金預金や固定資産などの資産科目と未払金や借入金の負債科目を、相続税評価額で計算していきます。
評価明細書の「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」に当てはめて計算していきます。
各科目別に相続税評価額の計算方法は、次の機会に説明いたします。