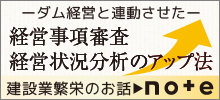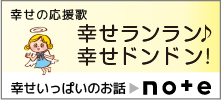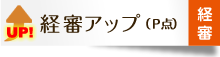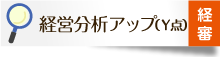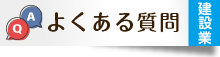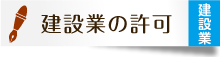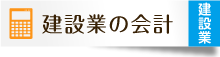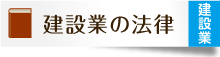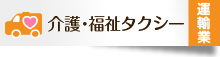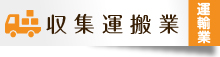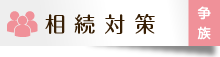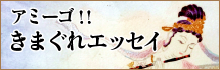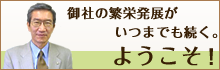日本にも、はるか昔、富士王朝の時代がありました。
伊集院卿氏の著書「富士王朝の謎と宮下文書」によれば、次のように記載されています。
「はるか遠い昔、富士北麓(ほくろく)の平原に、神々が来臨(らいりん)した」とあり、その伝説によれば、富士山を聖なる山として尊崇の念を抱いた神々は、北側の麓(ふもと)の地を「高天原(たかまのはら)」と名づけて住み着き、荘厳な神宮を創建し、王朝を確立し、富士山を拠点として日本を統治したのだという。
まさに、天御祖神(あめのみおやがみ)が、三万年前にアンドロメダ銀河から二十万人の大船団を率いて、富士山の北麓に飛来されたという事ですね。
だが、徐々にその富士王朝は衰え、その血脈は大和の天皇家に取って代わられてゆき、大神宮には砂塵が降り積もっていった。
そして、富士山の大噴火によって、かろうじて命脈を保っていた神宮は溶岩と火山灰の下に埋もれ、かつての繁栄の証しは永遠に幻のものなった。
ところが、この消されかけた歴史をかろうじて書き留めたものがあった。それが、超古代史文献「宮下文書」である。
そして、その謎の古文献出現のドラマの舞台もまた、富士北麓(ほくろく)に位置する小村なのである。
さらに「宮下文書」が長い沈黙を経て再び胎動を始めたのは、江戸時代の文久三年(一八六三)のことです。あと数年で明治時代になる幕末の頃です。富士北麓の片隅には、幕末の激動に取り残されたかのように、ひっそりと営みを続ける、ひなびた農村がありました。それが明見村(あすみむら)です。現在は(山梨県富士吉田市小明見・大明見)です。
その地の小室浅間(おむろせんげん)神社の宮司を代々務めてきた家が、宮下家です。
この文久三年の冬に、宮下家の隣家から火災が発生し、宮下家に燃え移り、たちまち火災に包まれてしまいます。その時の宮下家の当主は「長太郎」であり、わずか十四歳でした。姉の「梅子」は十八歳でした。両親も長太郎も病弱で、火災から逃げるのが精一杯でした。
宮下家には、先祖伝来の宝物である古箱が、天井の垂木に結びつけられていました。「非常の際には必ずこれを守ること」。梅子は幼いころから親にそう教えられてきました。しかし、梅子自身はその宝物がいったいどんなものなのかは知りませんでした。というのも、その古箱については、江戸時代のはじめ以来、「開封したら目がつぶれる」と先祖代々言い伝えられてきたからです。
「ご先祖さまから受け継いだ大切な宝物を、なんとしても守り抜かなければ」という固い決意で、梅子は火災の中を、垂木に結びつけられていた古箱をもぎとり、用意していた大箱に入れました。
この時の火災は、宮下家を含めて六六戸に及んだといいます。しかし、宮下家伝来の「宝物」は、梅子の決死の行動のおかけで、かろうじて残ったという事です。
この「宝物」は、その後も開封されることなく時間が流れます。宮下家を襲った明美村のあった大火事からは、すでに二十年の歳月が流れ、明治十六になっていました。「開けたら目がつぶれる」という教えは守られつづけていたのです。
しかし、ついに古箱の蓋が恐る恐る開けられる事になります。すると、なかから現れたのは、巻紙に記された古文書で、それもじつに膨大な数の古文書でした。これこそ、後に世を震撼(しんかん)させることになる、超古代史文献「宮下文書」だったのです。宮下家に脾臓されていた「宮下文書」の写真も掲載されていました。
ところが、発見された「宮下文書」が広く公にされるまでには、これからさらに四十年近い歳月を必要としました。
このような経緯があって、「宮下文書」が現代に伝えられたのですね。日本文明のルーツを少しだけ学ぶ事ができました。ありがとうございます。