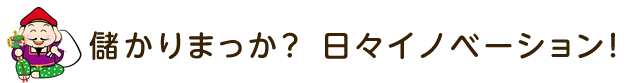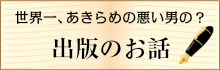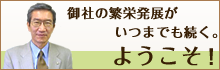私は、高校時代から小説家に憧れて、夏目漱石、森鴎外、三島由紀夫らの多くの書籍を読みました。彼らは一流と言われる作家です。一流作家と比較しているわけではありませんが、自分には才能がないと悟り、きっぱりと小説家になることを断念しました。
夏目漱石は、文部省派遣の第一回留学生としてイギリスへ行き、帰国後、一高や東京帝大の英文学の講師などをしていました。その後、大学講師を辞め、朝日新聞の連載小説を担当する作家になったわけで、それだけでも、当時としてはセンセーショナルなことではあったようです。
ただ、彼には、小説で食べていけるだけの基礎的な蓄積がありました。当時、漱石は、鴎外と並んで日本最高の知性を持った方でしょう。また、日本だけでなく東洋のなかでも、ほかに類を見ないほどの教養を持っている方でもあったでしょう。
その意味で、書く種が尽きないだけの勉強はされていたと思います。日本の文学のみならず、漢籍も読めましたし、留学して英文学の勉強までしてきました。要するに、ほかの人とは素養が全然違うわけです。普通の小説家と基礎がまったく違うので、書くことに事欠かなったでありましょう。
また、彼の奥さん(夏目雅子)が書いたものを見ると、「漱石がロンドンにいたときに、同僚から、『漱石、発狂せり』という電報が来ていた」というような話がありました。さらに、日本でのことになりますが、一緒にいた奥さんから見ても、「自分の旦那はちょっと狂っているのでないか」と思うような奇行(きこう)がたくさんあったらしいです。
やはり、制作を続けるというのは、それほど厳しいことなのでしょう。漱石のように、ほかの人とは知性の差、教養の差、環境的な差、才能の差が圧倒的にある人であっても、新聞に次々と小説を書いて食べていくのは簡単なことではなかったわけです。
ともかく、漱石という人は、妻から発狂しているように見えるほど、奇行が激しく、気性の上がり下がりが激しかったようですが、「それほど、創作の仕事というには厳しいものなのだ」ということでしょう。
あるいは、三島由紀夫にも、同じようなところはあったのでしょう。
彼は、若いうちから才能を発揮し、高校時代に書いた小説(花ざかりの森)あたりで文壇に出てくるような方でした。学生時代にはすでに小説を書いていたわけです。また、学業も優秀であり、東大の法学部を出て、大蔵省に入り、一年もたたずに辞めて作家になりました。
三島は、「欧米の作家のように、三年か四年に一回大作を書いて、あとは楽々と、カジキマグロでも釣りながら、ヨットの上で思いを巡らせて、十分、充電し、次の準備をしたい。何年かに一回、大作を書いて食べていけるぐらいの身分になりたい」というようなことを思っていたのでしょう。
ところが、彼ほど才能のある人であっても、結局、そうようにならずに、毎年毎年、書き続けないと食べていけなかった現実があります。どうやら、『境子の家』のような大作を書いたあたりで、「欧米の作家並みに、何年かは遊んで暮らせる生活」を目指していたようですが、なかなか、そうはなりませんでした。
一流といわれる人であっても、勝ち続けていくというか、生き残っていくというのは、実に大変なことです。
「努力していることが当然。才能があって当然。それでも勝ち残れない。生きに残れない」。これが現実の世界であります。
最近では、日本を代表するような「芥川賞」や「直木賞」を受賞されても、食べていけない時代です。この業界だけではなく、他の業界でも同じことだと思います。
非常に厳しい時代ですが、潜在意識をフル回転させて、勝ち続けていきましょう。