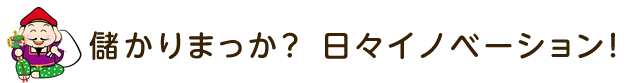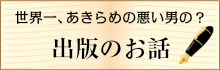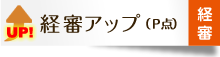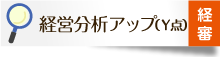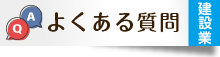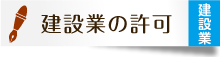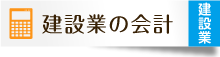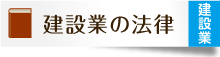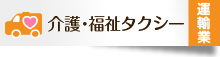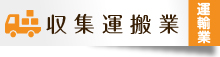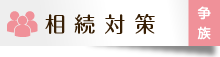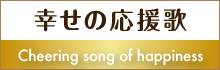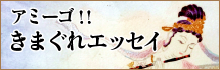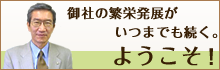松下幸之助さんの「人を活かす経営(PHP研究所)」に「説得なき説得」というタイトルで、面白い話が書かれていました。
三代将軍の徳川家光と老中の阿部豊後守(あべぶんごのかみ)のお話です。
家光がある年の春、狩に行った日のことです。狩から帰った家光が風呂に入ったときに、何を勘違いしてしまったのか、風呂係りの者が誤って熱湯を家光にかぶせてしまいました。家光の肌はたちまち赤くただれてしまい、家光は激怒しました。平謝りに謝る風呂係をあとにして部屋に戻ると、すぐに老中の阿部豊後守を呼び、「あの風呂係は不届き者だ。ただちに死刑を申し付けよ」と命じました。
死罪とはちょっと乱暴すぎますが、しかし、将軍の命令だから仕方ありません。阿部豊後守も「はい、かしこまりました」とその命令をそのまま受けました。ところが、いつもはそれでそのまま引き下がっていくのですが、このときは、次の間にさがると家光の側近の家来たちに、1つの頼み事をしました。「上様のご気分がおちつき、おだやかになったときに、私に知らせるように」と言って、ひとまず退去していきました。
夜になり、家光は食事をとると気分も落ち着き機嫌もなおったようです。その日の狩のはなしや成果なども話し始め、だんだん笑顔も見せるようになってきました。そこで側近の家来は、「上様のご機嫌がなおりました。非常になごやかなご様子です」と伝えました。これを聞いた阿部豊後守は、ただちに登城し家光に面会し、「先ほど、風呂係に罰を与えるようご指示いただきましたが、私はその内容をどうもあまりはっきりと覚えておりません。誠に申し訳ありませんが、もう一度ご指示願いますか」。
家光は、すぐには答えず、阿部豊後守の顔を見ながらしばらく考えていた。そしてやがて話し始めました。
「あの者は、まったくの不注意からあやまちをおかした。だから八丈島へ流罪を申し付けるようにせよ」。家光の指示をうけて、阿部豊後守は「かしこまりました」と引き下がりました。阿部豊後守が退出すると、家光のそばにいた側近の家来たちが、さっそく阿部豊後守をサカナにして、先ほどは、死罪にせよという支持を聞いて、阿部豊後守はたしかに「かしこまりました」と言ってさがった。それなのに、もう忘れてしまったらしい。阿部豊後守さえ、上様のご指示を忘れるほどであれば、たとえ我々が忘れることがあっても、それは仕方があるまい。「そうだそうだ」と、口ぐちに言いました。
これを耳にした家光は、にっこり笑って言いました。「あの豊後守が忘れたりするものか。ちゃんと覚えているのだ。ただ死刑に処するということは、天下の政治の中でもとくに慎重に念を入れて行うべきことだ。豊後守はその事を知っていて、私に念を押しにきたのだ。それで私も考え直して、死刑より罪を軽くして、流刑にしたのだ。豊後守のやり方は本当にゆきとどいている。それよりむしろ、一時の感情で死罪を口にした私のほうが恥ずかしいと思う」。これを聞いた家来たちは、恐れ入って、もう何も言えませんでした。
阿部豊後守は、家光が死刑にせよと命じたこと自体は「かしこまりました」と、そのまま受けています。しかし、それはそれとして実行には移しませんでした。感情的になっているときは、たとえ天下の名君家光でさえも、正しい判断、適切な判断をくだすことはできないのです。しかし、それが適切でないと指摘して改めさせようなどとすれば、なおさら感情を高ぶらせてしまう。それでは説得することは出来ません。
阿部豊後守の場合は、説得それ自体をしていません。いわば説得なき説得とも言えます。もう一度聞き直す、タイミングを見きわめて確認し直す、ということをしただけです。そうすれば、この例のように、場合によってはそれだけで効果的な説得をしたのと同じことになります。
我々は、つね日頃、説得と言えば言葉を費やして行うものだと考えがちですが、必ずしも、そうではない場合もあるわけです。こちらの思うこと、意図することが相手に伝わる、そういう説得なき説得というものがあるのですね。。
これは、実際にはなかなか難しいことかもしれませんが、大事な事だと思います。