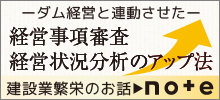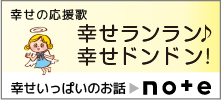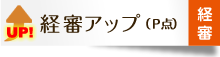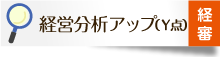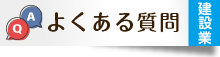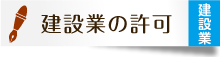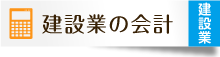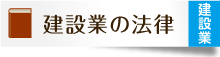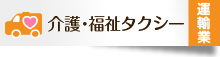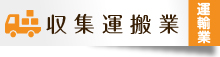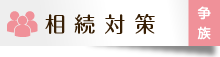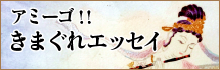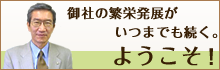準資産価額方式の概要については、前回の記事で紹介いたしました。
今回は、準資産価額方式の科目別の相続税評価額について説明いたします。
つまり、課税時期の決算書(通常、直前期末)に基づき、現金預金や固定資産などの資産科目と未払金や借入金の負債科目を、相続税評価額で計算していきます。
評価明細書の「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」に当てはめて計算していきます。
それでは、各科目別に相続税評価額の計算方法を見ていきましょう。
1.資産の科目別の相続税評価額
⑴ 預金
預金の相続税評価額は、預金金額と既に発生している利息分を含めて評価します。但し、利息に係る源泉所得税額は控除します。
⑵ 受取手形
受取手形の相続税評価額は、期限未到来分の割引料相当額を控除した回収金額により計上します。支払期日が到来しているもの、課税時期から6ヵ月を経過するまでに支払時期が到来するものは券面額で評価します。課税時期から6ヵ月を超えて支払期日が到来するものは、回収可能額で計上します。
⑶ 売掛金・貸付金・仮払金
売掛金の相続税評価額は、課税時期現在の回収不能額を控除して評価します。既経過利子があれば加算します。貸付金も仮払金も同じです。
⑷ 棚卸資産(製品・仕掛品・原材料)
財産評価基本通達の133に棚卸資産の評価方法が記載されています。次のとおりです。
|
133 たな卸商品等の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。ただし、個々の価額を算定し難いたな卸商品等の評価は、所得税法施行令第99条≪たな卸資産の評価の方法≫又は法人税法施行令第28条≪たな卸資産の評価の方法≫に定める方法のうちその企業が所得の金額の計算上選定している方法によることができる。(昭41直資3-19・平12課評2-4外改正) (1)商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、その価額のうちに含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売までにその販売業者が負担すると認められる経費(以下「予定経費」という。)の額及びその販売業者がその商品につき納付すべき消費税額(地方消費税額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。 (2)原材料の価額は、その原材料を使用する製造業者が課税時期においてこれを購入する場合の仕入価額に、その原材料の引取り等に要する運賃その他の経費の額を加算した金額によって評価する。 (3)半製品及び仕掛品の価額は、製造業者がその半製品又は仕掛品の原材料を課税時期において購入する場合における仕入価額に、その原材料の引取り、加工等に要する運賃、加工費その他の経費の額を加算した金額によって評価する。 (4)製品及び生産品の価額は、製造業者又は生産業者が課税時期においてこれを販売する場合における販売価額から、その販売価額のうちに含まれる適正利潤の額、予定経費の額及びその製造業者がその製品につき納付すべき消費税額を控除した金額によって評価する。 |
上記の方法で適正に評価されているなら、帳簿価額で評価できると考えます。建設会社の未成工事支出金勘定も適正に評価されているなら同様です。
但し、帳簿価額が適正でないなら、適正に再評価し、相続税評価とする事が可能だと考えますが、その法人の決算そのものに疑問が生じ、別の観点からの問題点が発生します。
ここでは、帳簿価額が適正であることを前提にしたケースを想定していますので、帳簿価額で評価しますと解説しておきます。
⑸ 未収入金
未収入金の相続税評価額は、課税時期現在の回収不能額を控除して評価します。
⑹ 前払費用
財産性がない場合の前払費用や長期前払費用は、相続税評価額も帳簿価額も記載しません。
⑺ 建物(通常の場合)
建物の相続税評価額は、個人の事事業用資産と同じように固定資産評価額により評価します。減価償却資産の減価償却期間は、仮決算方式の場合は課税時期までの期間で計算し、直前期末方式の場合は直前期末までの期間で計算します。
圧縮記帳を行っている場合は、圧縮記帳前の取得価額をもとに減価償却の計算をします。
建物の帳簿価額は、取得価額から減価償却累計額を差し引き、減価償却超過額をプラスして計上します。また、特別償却準備金や圧縮記帳に係る引当金または積立金がある場合は、帳簿価額から控除します。
⑻ 建物(課税時期前3年以内に取得した建物)
但し、課税時期前3年以内に取得した家屋等は、課税時期における通常の取引価額で評価します。固定資産評価額で評価しません。家屋の通常の取引価額は、取得価額から課税時期までの期間の減価償却額を控除した金額により評価できます。
(参考)
課税時期前3年以内に取得または新築した土地等・建物等は、課税時期の通常の取引価額(時価)によります。課税時期の通常の取引価額に相当する金額(帳簿価額)が、課税時期の通常の取引価額と比べて近似値である場合やほぼ同等と認められる場合は、帳簿価額を友情の取引価額として評価できます。(評基通185のかっこ書)
但し、以下の事実がある場合は、帳簿価額が課税時期の通常の取引価額に相当すると認められない可能性があります。
① 取得後、課税時期までに資産価額に大きな変動があった場合
② 高額所得または定額取得に該当する場合
③ 買い急ぎの理由がある場合などです。
この取扱いは、主に不動産の時価と相続税評価額との開きを利用した株式の純資産価額の引き下げ対策に対処したものです。
⑼ 建物附属設備
建物附属設備に相続税評価額はないため評価しません。家屋と構造上一体となっているものは、家屋の固定資産税務署長に評価が反映されていりため、家屋の評価に含めて評価します。
⑽ 構築物
構築物の相続税評価額は、再建築価額から建築時から課税時期までの期間に定率法により計算した減価償却費の額を控除した額の70%で評価します。
⑾ 機械装置・車両運搬具・工具器具備品
機械装置・車両運搬具・工具器具備品は、原則は売買実例価額、精通者意見見積価額等を参酌して評価します、実務上、帳簿価額でも認められると考えます。
⑿ 土地(通常の場合)
土地の相続税評価額は、課税時期の属する年分の路線価等により評価します。
帳簿価額は、土地圧縮記帳引当金の額があれば帳簿価額から差し引き、土地圧縮限度超過額があれば帳簿価額に加えます。
⒀ 土地(課税時期前3年以内に取得した場合)
課税時期前3年以内に取得した土地は、課税時期における通常の取引価額で評価します。路線価等で評価しません。但し、帳簿価額が課税時期の通常の取引価額に相当すると認められる場合は、帳簿価額により評価ですることが認められています。
参考事項に関しては、上記⑻の「建物(課税時期前3年以内に取得した建物)」と同様です。
⒁ 建設仮勘定
建設仮勘定の内容が課税時期に建築中の家屋の場合には、その家屋の費用原価に70%を乗じた価格で相続税評価をします。
⒂ 借地権
借地権の相続税評価額は、路線価に基づいて計算した額で評価します。帳簿価額は、無償取得による借地権の場合は、0を記載します。
⒃ 投資有価証券(上場株式)
投資有価証券のうち上場株式の相続税評価額は、課税時期の最終価格等により評価します。
2.負債の科目別の相続税評価額
帳簿価額に計上のないものでも原則、課税時期(直前期末方式は直前期末)に債務が確定しているものを計上します。例えば、未納の公租公課、未払利息、支給が確定した退職金などがあります。
反対に、帳簿価額に計上があるものでも、債務として確定していないものは計上しません。例えば、貸倒引当金、返品調整引当金、賞与引当金、圧縮記帳引当金、特別償却準備金などがあります。
それでは、負債の科目について説明していきます。
⑴ 支払手形
帳簿価額により評価します。
⑵ 買掛金
課税時期現在において、事実上、支払を要しない金額を減算します。
⑶ 借入金
帳簿価額により評価します。
⑷ 未払金、未払費用、前受金、仮受金、預り金
帳簿価額により評価します。
⑸ 未払税金
課税時期現在の金額により評価します。
⑹ 退職給付債務
課税時期における要支給額により評価します。
以上、準資産価額方式の科目別の相続税評価額について説明いたしました。