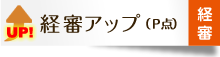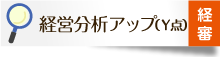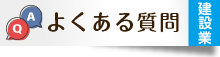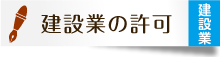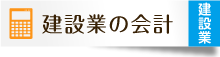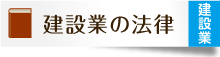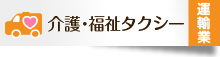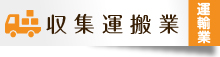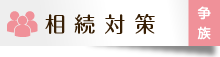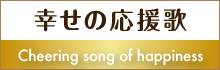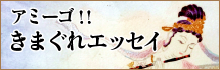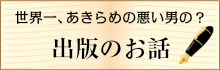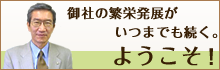現在の経審(平成20年改正後)は、会社経営にとって重要な指標が凝縮されています。
特に、経営規模の評価項目の一つに「自己資本額および平均利益額(X2)」があり、経営の要諦になる重要な評価項目です。この評価項目に重点を置いて、経営を進めるられることを強く望みます。今まで述べてきました経営分析(Y点)の8指標も重要ですが、「自己資本額および平均利益額(X2)」も決算書の数字が反映しますので、ある意味、9番目の経営分析指標とも言えます。
この評価項目は、現在の経審では、売上高の規模に関係なく、資本金の充実や繰越利益金の余剰金を伸ばしていくことで、単独でP点やY点を伸ばすことができます。改正前は売上高と連動していましたので、あまり評点アップが望めませんでしたが、現在の経審の自己資本額は違います。つまり、売上高に連動していませんので、自己資本額を上げて、平均利益額を上げれば、単独でアップ対策がとれるということです。
自己資本額は、資本金を増やすことで対策が可能になります。しかし、平均利益額の利益剰余金に関しては、短期的な対策では評点アップが図りにくいと考えますが、私がいつも言っている「無借金経営」「ダム経営」を日々の実践行為として、信念を貫いて実践なさってください。必ず「平均利益額」はアップします。対策については、後から述べます。
この「自己資本額および平均利益額(X2)」は、自己資本額評点と平均利益額評点を用いて計算します。自己資本額は「自己資本額評点の算出式」の表で、平均利益額も「平均利益額評点の算出式」の表で、それぞれ評点を算出します。そして2つの評点を足して、2で割ります。これが「自己資本および平均利益額(X2)」の評点になります。
|
(算式は) X2=(自己資本額評点+平均利益額評点)÷2で計算します。 |
自己資本額とは、決算書のうち貸借対照表の資産総額から負債総額を差し引いた純資産額の合計額をいいます。簡単にいえば、資本金+繰越利益金です。他に別途積立金などがあれば、それも足します。
平均利益額の利益とは、支払利息、法人税等、減価償却費を除いた利益を基準にしています。つまり、営業利益に減価償却費を足した金額になります。その2年平均額です。
綜合評定値(P点)に占めるウエイトは、15%です。平成20年改正前の10%から15%に引き上がられています。さらに、評点の上限も954点から2,280点まで引き上げられ、非常に重要度の高い評価項目となっています。
P点に換算しますと、X2×0.15(ウエイト15%)となります。自己資本額がマイナスの場合は、0円とみなして評価されます。
⑵ 自己資本額が単独でアップする
改正前の自己資本額は、年間平均完成工事高に対して、どの程度の自己資本があるかを評価していました。
しかし、現在の経審(平成20年改正後)は、自己資本額そのものが絶対額と評価され、自己資本額が大きいほど評点が高くなります。改正前のように、同じ自己資本額でも年間完成工事高が上がれば、逆に自己資本額の評点が下がるという現象が起こりません。利益を多く残した強い経営体質が評価されます。無借金経営、ダム経営の実践に尽きます。ダム経営は、経審だけでなく、心に余裕を持って、経営を進めていくことができます。
⑶ 増資の勧め(自己資本の充実)
個人的に資金余裕があれば、増資をお勧めします。グループ会社等の応援も含めて、自己資本の充実のために、増資計画をなさってください。
すぐに増資資金がないならば、役員報酬から一定額を天引する形で、増資預り金として積立しておいて、中長期的に増資計画を進めてください。役員報酬を全部持ち帰るのではなく、将来の増資積立金に当てることも、ダム経営に近づける一歩です。
⑷ 平均利益額(利益剰余金)
平均利益額(利益剰余金)は、短期的な対策で評点アップが望めません。
繰越利益金は長年の営業成果が蓄積された智慧と汗の結晶ですから、飛躍的に向上することはありません。しかし、普段の経営の積み重ねですので、日々の実践行為として、常に念頭におき、余剰金を増やことに的を絞ってください。建設業は余剰金が勝負です。必ず工事代金の立替金が発生しますので、余剰金がいかに大切か、社長自身が一番よく知っています。
また平均利益額は、経営分析の8指標の全部に関連する評価項目です。8指標を再現しますと下記のとおりです。
|
平均利益額(利益剰余金) ①金利を減らすこと。 (借金を減らすこと) ②粗利益を増やし、確実に経常利益を上げること。 ③自己資本を増やすこと。 ④総資産をスリム化すること。 |
第1位 純支払利息比率(29.9%) |
|
第2位 総資本売上総利益率(21.4%) |
|
|
第3位 自己資本比率(14.6%) |
|
|
第4位 負債回転期間(11.4%) |
|
|
第5位 自己資本対固定資産比率(6.8%) |
|
|
第6位 売上高経常利益率(5.7%) |
|
|
第7位 営業キャッシュフロー(絶対額)(5.7%) |
|
|
第8位 利益剰余金(絶対額)(4.4%) |
この平均利益額と8指標の関連性が明確になり、いかに平均利益額が重要な評価項目か理解できます。
平均利益額(利益剰余金)のアップ対策も、理屈対策で述べたとおり、①金利を減らすこと(借金を減らすこと)、②粗利益を増やし、確実に経常利益を上げること、③自己資本を増やすこと、④総資産をスリム化することの4つと同じ対策になりました。
また「アップ対策3(利益と納税についての考え方)」でも述べましたが、利益を上げ、利益余剰金を増やしていくことは、誰でも知っています。増資をすれば、資本金が増え、バランスが良くなり、経審がアップすることは、みんな思っていますが、実行できないだけです。なぜ実行できないのか、お金がないからです。
それを達成するには、経営者のマインドを変え、達成させる情熱と中長期的な努力で可能になります。その一番最初の経営者のマインドを変えない限り、次に進むことができません。その最大のネックが納税意識です。この納税意識を変えない限り、経審アップや分析アップの真の対策になりません。
平均利益額(利益剰余金)を増やしていくには、経営者のマインドを変えてください。納税意識を高めてください。これに尽きます。