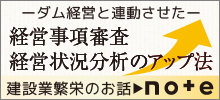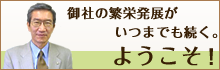建設業会計を学ぶためには、受注した建設工事の収益(売上高あるいは完成工事高)をいつどのように計上するか、という課題がある。
建設業に代表される業務請負型の産業においては、他の産業と異なる固有の特性から建設業の収益認識について、伝統的に、次の2つの基準が並存していた。
まず、工事完成基準とは、商品・製品の販売業務と同様に、収益の実現の時を、工事が完成し発注者に引き渡し完了した時とする方法である。工事代金(対価)の受領は、その完成・引渡しをもって確定するという商慣習に支えられたものと考えることができる。わが国では、後述する税制改正まで長い間、ほとんどの建設企業において、この工事完成基準が建設工事の収益認識基準として採用されてきた。
次に、工事進行基準とは、建設工事を受注した後、完成・引渡しにいたる間、当該工事の収益は、工事の進捗とともに順次発生しているので、収益の認識は、工事の進行とともに把握していくという方法である。建設工事の対価の受領は契約時に成立しており、工事が進むにつれてその対価も部分的に確定していくとする考えに支えられたものと考えることができる。企業における実態業績の適切な開示という強い要請とともに、国際会計基準が原則として採用するという方式である。
このような状況下、わが国の「企業会計原則」は、建設工事の収益認識のあり方を次のように定めている。
「長期の請負工事に関する収益の計上については、工事進行基準又は工事完成基準のいずれかを選択適用することができる。」(企業会計原則注解7)
企業会計原則は法規ではないが、他の法規範の制定、改廃において尊重されるべき一般に公正妥当な会計慣行の収斂と理解されている。会社法や金融商品取引法の下にある諸会計基準も、建設工事の収益認識について特段の規定をしていないことから、この解釈が会計基準としての基本原則になるものと考えられていた。ただし、この注解は、「長期の請負工事」の収益認識における選択的な適用を規定したもので、短期の請負工事はこの適用を受けないから、一般の製品製造販売に準ずる実現主義による収益認識すなわち工事完成基準が適用されるものと解されている。
ところが、日本の企業会計基準委員会は、2008年(平成20年)、企業会計基準として「工事契約に関する会計基準」と「工事契約に関する会計基準の運用指針」を公表し、平成21年4月1日以降開始する事業年度に着手する工事契約に適用する会計基準が確定した。これによって、工事完成基準と工事進行基準の並存の状況は、原則を工事進行基準に置く認識基準へと大きく方向転換した。
この目的は、国際会計基準とのいわゆる「会計コンバージェンス(収斂化)」に他ならない。
さらには、わが国の法人税法は、1998年(平成10年)、長期(2年以上)で大規模(50億円以上)の建設工事については、工事進行基準をすべての企業に対して強制的に適用するよう、その規定を改正した。その後、適用基準は1年-10億円以上にまで引き下げられ、法人税法のいう長期大規模工事には、工事進行基準が導入されたことになった。